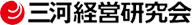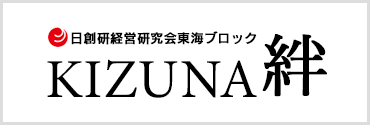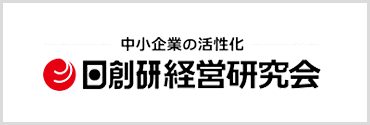当会について
日創研経営研究会「三河経営研究会」
- ホーム
- 当会について
日創研経営研究会
「三河経営研究会」とは
準備中…
会長方針
具体的に明確に肯定的に『目標』を持ち、 可能思考を発揮して、業績を向上させよう!
日創研三河経営研究会 2025年度 会長 酒井勝規
日本経済は約30年続いたデフレ時代から、原材料価格の値上がりによるインフレ時代の入口に立たされており、
我々中小企業にとっても、仕入価格の高騰・エネルギーコスト上昇・最低賃金の引上げと経営を取り巻く環境は
さらに厳しい時代に突入しております。
この大きく変わる時代を乗り越えていくためには、具体的に明確に肯定的に『目標』を持ち、可能思考能力を発
揮して行動していく事だと考えております。
そして可能思考を学んだ仲間が集い発足した日創研三河経営研究会は、2025年に30周年の年を迎えます。30年
間続いている三河経営研究会の強みを生かし、知識や経験を先輩経営者から学び、未来に繋がる技術を若手経
営者から学ぶ、「共に学び共に栄える」理念の基、会員企業の業績向上に繋がる一年とします。
-
(1)委員会出席率:70%
(2)会員拡大:5名
(3)経営計画書作成率:85%
各委員会テーマ
・経営理念委員会・・・経営の根本理念に関する研究(例会出席率:70%)
・経営戦略委員会・・・時代の環境変化に対する経営計画書作成の推進(経営計画書作成率:85%)
・ありがとう経営推進委員会・・・ありがとう経営推進・実践についての啓発及び活動
(公式教材導入率 13の徳目:50%、理念と経営:50% *全国大会in浜松 副主幹としての活動)
・拡大委員会・・・入会、退会に関すること(会員拡大:5名)
・総務委員会・・・定款、諸規定に関すること(運営のDX化推進)
(1)委員会出席率:出席率70%
1)委員会次第のフォーマットを活用した委員会運営(理事会報告、本部研修の案内など)
2)経営計画書(会員スピーチシート)を軸にした学びの場を設営
3)委員会ガイドラインを活用した委員会開催(目標:全会員が4回以上の委員会参加)
4)委員会三役会(担当副会長・委員長・副委員長)の定期開催
(2)全国3大事業、東海ブロック事業への積極的な参加
1)「13の徳目朝礼」東海ブロック大会(2月)
2)全国大会in浜松(5月) 全会員100%参画
3)東海プレ経営発表大会(8月) 目標:出席率30%(出席者15名、内発表者5名)
4)オンライン特別研修(9月) 目標:出席率30%(出席者15名)
5)全国経営発表大会(11月) 目標:出席率30%(出席者15名、内発表者5名)
出席者を増やし、経営計画書と触れる場を積極的に推進する
(3)日本創造教育研究所開催の本部研修受講促進 受講率:50%
1)本部研修受講の感想を全体メールに上げて情報共有する
2)総務委員会にて全体メールを確認後、研修受講補助金を支給する
エグゼクティブ・リーダーシップ(目標実現)セミナー参加補助 一人10,000円(目標:25名)
3)エグゼクティブ・リーダーシップ(目標実現)セミナーの参加 理事監事100%
(4)公式教材(『理念と経営』、『13の徳目朝礼』)の活用と導入の促進
1)13の徳目朝礼東海ブロック大会参加
2)8月総会後に、公式教材を活用した勉強会の開催
(5)入会トライアル(4月~7月):拡大5名
1)経営計画書発表例会を含めた、4ヶ月間の開催
2)「理念と経営」経営者の会との連携(4ヶ月間の開催日、事前確認)
トライアル期間中は経営者の会へ配属を行う
岡崎支部:杉本支部長、三河支部:下島支部長、豊田支部:安本支部長
3)トライアル生の東海ブロック経営発表大会参加 入会予定者:目標3名
4)トライアル生の全国経営発表大会参加 新入会員:目標3名
(6)質の高い、例会や勉強会の開催
1)レクチャラーなど、講師による例会などの開催(4月・6月・10月)
2)オブザーバー(会員企業の社員さん、経営者、経営幹部)の参加促進
(7)三河経営研究会の人財育成
1)理事候補者の育成 正会員化:90%
2)副委員長の理事会オブザーバー参加(担当委員会議案上程時)
3)新入会員の理事会オブザーバー参加
(8)運営面での仕組づくり
1)絆システムの活用(事業の案内、出欠管理、活動報告、会員手帳)
2)例会開催などマニュアルを活用した運営
※レクチャラ―例会マニュアルの活用
※過去の理事会議案書の活用(改善点を生かす)
※レクチャラー講師アテンドマニュアルの確認(本部支給)
※例会運営フローシートの活用(絆システム・電子手帳)
3)会費や参加費の徴収に関して業務の改善
4)AIを活用した理事会議事録のDX化
5)年4回の業績アンケート(3月・6月・9月・12月)
組織図